はじめに
こんにちは!2025年6月1日にSIerからGMOペパボに転職した ikechi です。
現在、ハンドメイドマーケット「minne」のWebエンジニアとして開発を担当しています。 GMOペパボで働き始めてから、前職のSIerとは異なる開発環境や文化の違いを日々実感しています。
本記事では、この半年で私が体験し、実感したSIerと事業会社の違いについて、詳しくお話ししたいと思います。
転職の背景
前職のSIerでは、要件定義から運用まで一通りの開発プロセスに携わり、幅広い経験を積むことができました。しかし、エンドユーザーとの距離をもっと縮め、プロダクトを通じて直接的な価値提供に携わりたいという想いが日々強くなっていきました。
そんな中でGMOペパボと出会い、「みんなと仲良くすること」「ファンをつくること」「アウトプットすること」という 「わたしたちが大切にしている3つのこと」 に強く共感しました。
さらに、面接での会話を通じて、この文化のもとでプロダクトへの貢献だけでなく、 自身の技術的な成長も加速できる環境 であると確信したため、転職を決意しました。
開発環境・技術要件の変化
AIをフル活用した開発スタイル
GMOペパボに転職して最も驚いたのは、最新のAIツールを積極的に取り入れ、フル活用する開発文化です。
前職では利用できるAIツールに制限がありましたが、GMOペパボではリリースされた新機能やツールを、すぐに業務で活用できる環境が整っています。コード生成、レビュー支援、ドキュメント作成など、開発の各フェーズでAIを活用することで、開発効率、開発者体験が劇的に向上したことを体験しています。
さらに印象的なのは、エンジニア以外の職種もAIを使いこなしていることです。デザイナーやディレクターがClaude Code Actionでプルリクエストを作成したり、分析のためのSQLを作成したりと、職種や経験年数に関係なく全員がAIを使いこなしています。
この先進的な環境は、GMOペパボのエンジニアバリューである「すべてが自分ごと」をまさに体現していると感じます。職種の垣根を越えて全員がAIツールを使いこなし、それぞれが課題解決に主体的に取り組む文化に日々刺激を受けています。
求められる技術の幅
minneチームのエンジニアは、フロントエンド、バックエンド、インフラと幅広い技術領域をカバーしています。
前職では役割分担が明確な体制で安定したプロジェクト遂行が特徴でしたが、事業会社では一人が複数領域に関わるスタイルで、求められるスキルの幅が変わりました。 そのため、特定領域にとどまらない横断的な知識が重要です。
最初はハードルが高く感じることもありましたが、インフラ専門チームのサポートやシニアエンジニアの方々からのアドバイスを受けながら、成長を遂げることができています。
大規模システムの運用・保守
10年以上続く大規模プロダクトを扱う中で、よりレベルの高い技術的対応に取り組む機会が増えました。
SIerでは、こうした重要度の高い課題はプロパーエンジニアが対応することが多く、委託先メンバーが関わる機会は限られていました。入社後はこういった重要度の高い課題に携わることができ、技術的な成長と大きなやりがいを得ています。
チーム・組織文化の特徴
多様なステークホルダーとの協働
前職と比較し、関わる人の幅が大幅に広がったことに驚いています。
モバイルアプリチームや業務委託メンバーに加え、オフショアメンバーなど、国内外の多様なバックグラウンドを持つメンバーと日常的に連携しながら開発を進めています。
これまでは、社内の限られたメンバーや同じ委託先企業内でのやり取りが中心でしたが、現在は多様なバックグラウンドを持つメンバーと連携しながら開発を進めています。 中には英語を使用する場面もあり、国際的な開発経験を積める貴重な機会になっています。
アウトプット文化
GMOペパボはアウトプットを重要視する文化が根付いています。 技術ブログの執筆、社内勉強会での発表、カンファレンスでの登壇など、様々な形で知識や経験を共有することが推奨されています。
これまで登壇経験が全くなかった私でも、チームメンバーから背中を押してもらい、入社後わずか1ヶ月で LTに挑戦できました。
9月20日には、約500人が参加する ServerlessDays Tokyo 2025 という大きな舞台で登壇を実現しました。こうした経験はGMOペパボに入社していなければ得られなかったと思っています。

1月にはBuriKaigiへの登壇も決定しており、この勢いを緩めずにさらなるアウトプットに挑戦していきます。
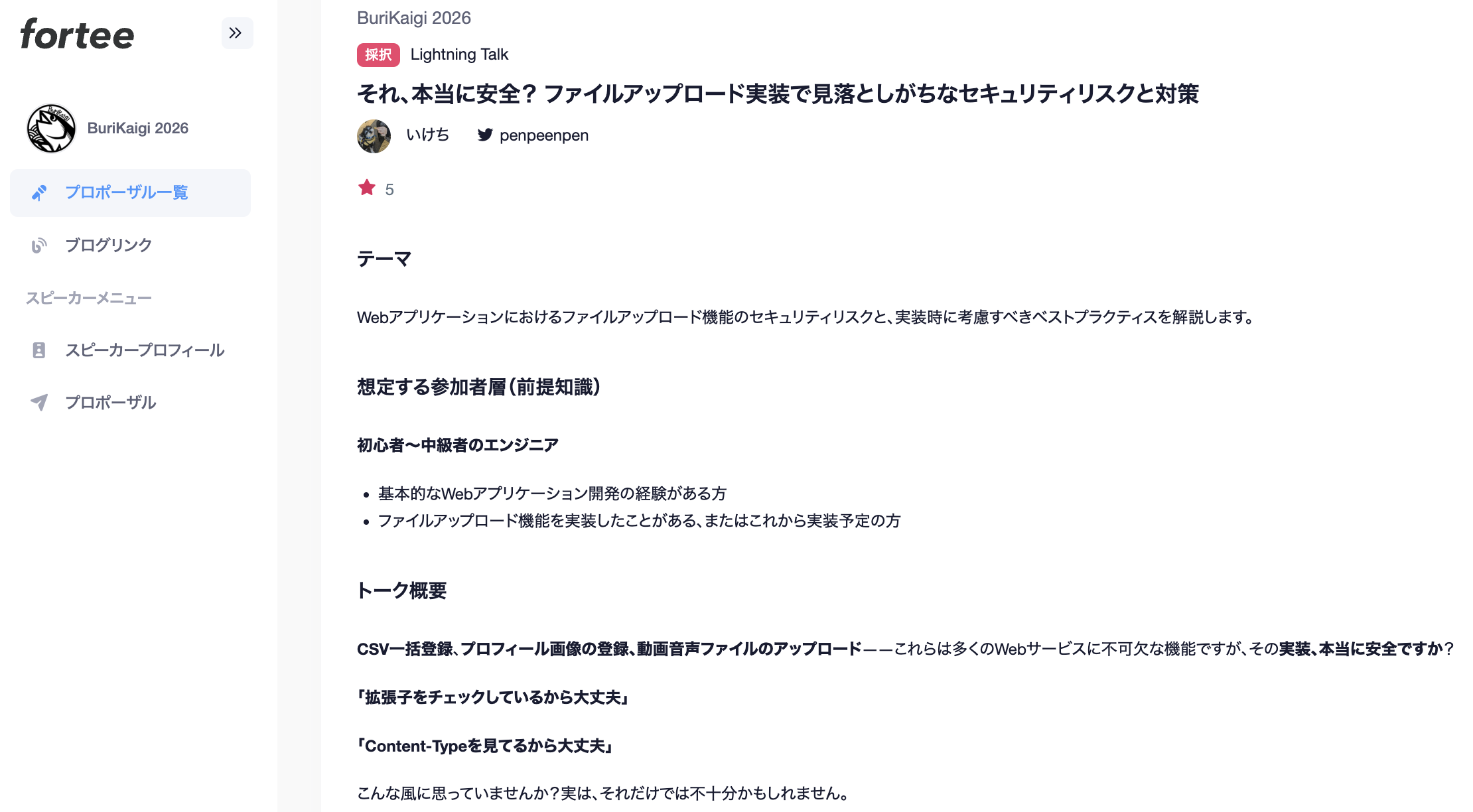
高いオーナーシップと事業理解
GMOペパボでは、エンジニアメンバーも事業の進捗や戦略を共有する事業部定例に出席し、ビジネス側の視点も持ちながら開発を進めています。これはSIerでは経験できていなかった貴重な経験であり、プロダクトの価値向上に直結する重要な要素だと認識しています。
こうした事業理解の深まりから、「自分たちのサービス」という意識が強く、エンジニアメンバーも積極的に改善提案や課題解決に取り組む文化があると見て取れます。
働き方の変化
GMOペパボの出社スタイル
前職のSIerはリモートワークが中心でしたが、GMOペパボは毎日出社のスタイルです。 最初は不安もありましたが、実際に働いてみて、対面でのコミュニケーションがもたらすメリットを強く実感しています。
相談や議論がしやすく、チームの一体感も前職と比べて向上したと思っています。 さらに、無料のご飯やカフェスペースもあるので、リフレッシュしながら快適に働くことができています。
半年で達成できた成果
以下は、入社後の半年で実現した成果です。
入社15営業日でクーポン上限額適用機能のリリース
最も印象的だったのは入社からわずか15営業日という短期間で、クーポン上限額適用機能をリリースしたことです。
GMOペパボならではの開発スピードと意思決定の速さを痛感しました。
この開発体験の詳細は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
一括発送処理の改善
これまでminneの作品の発送処理は1件ごとに行う必要がありましたが、CSVを使用した一括発送機能に対応しました。
この機能実装では、セキュリティ面でのマルウェア対策はもちろん、高負荷時のスケーリングを考慮し、サーバーレスアーキテクチャを積極的に活用しました。これにより、安定性と開発効率の両面で大きな改善を実現しました。 具体的な利用方法や詳細は、ヘルプページをご参照ください。

作品ページにAmazonPayボタンの設置
作品詳細画面にAmazonPayボタンを配置し、購入までの導線を大幅に短縮しました。
従来はカート画面を経由する必要がありましたが、この機能により作品詳細画面から直接購入フローに進めるようになりました。
これにより、外部からの流入時に即座に購入へ進めるようになり、ユーザー体験の向上を実現しました。
技術的には、従来のカート依存のフローとは独立した新しい購入フローを構築する必要があり、GraphQL APIの新規設計やAmazonPayとの連携処理など、多岐にわたる実装を行いました。
ユーザーの購入体験を向上させながら、作家の皆さまの販売機会拡大にも貢献できる機能をチームと共に形にできたことに大きなやりがいを感じました。

私たちが求める人物像
半年間GMOペパボで働いて感じた、「こんな人と一緒に働きたい」と感じる人物像を共有したいと思います。
新しい技術や手法に対して積極的な人
GMOペパボではAIツールの活用が日常的に行われており、新しい技術を恐れずに取り入れる姿勢が重視されています。「完璧でなくても、まずは試してみる」という好奇心がある人に向いている環境だと思います。
チームでの協働を楽しめる人
出社スタイルを活かした対面でのコミュニケーションを大切にし、お互いの成長を支え合える関係性を築ける人が活躍できる環境です。
アウトプットを通じて成長したい人
技術ブログの執筆や勉強会での発表など、学んだことを積極的に共有し、自分とチームの成長に還元する文化があります。「自分の成長を他の人にも還元したい」という想いを持った人にとって、理想的な成長環境が整っています。
まとめ
SIerから自社サービス開発への転職は、単なる勤務地の変化ではなく、働き方、思考、そしてエンジニアとしてのアイデンティティを根本的に変化させる経験でした。
入社後半年間にもかかわらず、ユーザーの反応が直接返ってくる自社サービス開発の大きな魅力を実感できています。
今後もこの刺激的な環境で成長を続け、チーム、プロダクト、そしてハンドメイドコミュニティの発展に貢献していきたいと思います!
